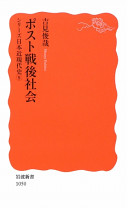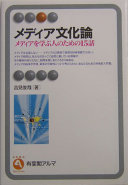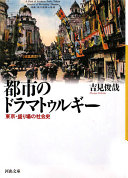吉見俊哉 (ヨシミ・シュンヤ)
1957年生まれ。都市論、文化社会学。東京大学大学院学際情報学府学際情報学教授。
(最終更新:2010年4月19日)
 10+1 DATABASE内「吉見俊哉」検索結果 (24件)
10+1 DATABASE内「吉見俊哉」検索結果 (24件)
[都市/テクスト]
九〇年代社会学/都市論の動向をめぐって | 若林幹夫
An Introduction to Books on Sociology: Urban Studies in the 90s | Wakabayashi Mikio
...ついていたからだ。八〇年代後半に刊行された吉見俊哉の『都市のドラマトゥルギー──東京・盛り場... ...るそうした試みはいまだ途上の段階にあるが、吉見俊哉編『二一世紀の都市社会学4 都市の空間 都市...
『10+1』 No.19 (都市/建築クロニクル 1990-2000) | pp.110-111
[Urban Tribal Studies 3]
トランスクリティックとエスノグラフィ | 上野俊哉
Trancecritique and its Ethnography | Ueno Toshiya
...きく問題にされていたことがよく理解できる。吉見俊哉は最近の論文、エッセイなどで、この時期のカ... ...っているのである。この立場は、ある意味では吉見俊哉による初期バーミンガム派の「抵抗」図式への...
『10+1』 No.15 (交通空間としての都市──線/ストリート/フィルム・ノワール) | pp.254-262
[都市の全域性をめぐって(下)]
共異体=共移体としての都市 | 若林幹夫
On the Totalization of the City (Part 2): A Polymorphic = Polydynamic City | Wakabayashi Mikio
...代都市空間の形成と民衆の『都市の体験』」[吉見俊哉編『都市の空間 都市の身体』 21世紀の都市社... ...)]等を、盛り場論としての都市論については吉見俊哉『都市のドラマトゥルギー』(弘文堂、一九八...
『10+1』 No.11 (新しい地理学) | pp.231-242
[批評]
東京論の断層──「見えない都市」の十有余年 | 中筋直哉
Dislocated Studies of Tokyo: The "Invisible" City in Recent Decades | Naoya Nakasuji
...いるのである。 4 都市のドラマトゥルギー──吉見俊哉の作品に見る八〇年代的都市論の困難 次に採り... ...における八〇年代の都市論─東京論の最高峰が吉見俊哉『都市のドラマトゥルギー』(弘文堂、一九八...
『10+1』 No.12 (東京新論) | pp.168-177
[論考]
歴史・観光・博覧会 第四回内国勧業博覧会と平安遷都千百年紀念祭の都市空間 | 笠原一人
History, Sightseeing, Exposition: Urban Space in "The 4th Exposition for Development of Domestic Industries" and "The 1100th Anniversary for Relocating the Capital to Kyoto" | Kazuto Kasahara
...クックの旅』(講談社、一九九六)。 ★四──吉見俊哉『博覧会の政治学』(中央公論社、一九九二)... ...商業会議所、一八九二年一一月)。 ★一一──吉見俊哉「文明への眼、未開への眼──シカゴ万博と日...
『10+1』 No.36 (万博の遠近法) | pp.164-177
[座談会]
「新しい地理学」をめぐって──地図の解体、空間のマッピング | 水内俊雄+大城直樹+多木浩二+吉見俊哉
On New Geography- Dismantling the Map, Mapping Space | Toshio Mizuuchi, Naoki Ohshiro, Taki Kouji, Yoshimi Syunya
多木──今日は「ニュー・ジオグラフィ」ないしは「ヌーヴェル・ジオグラフィ」──いずれ「新しい地理学」と呼ばれているものも、やがて「ニュー」や「ヌーヴェル」という...築をもたらした状況だと思います。 多木浩二氏吉見俊哉氏メタ地理学──地図の呪縛からの解放 多木─...
『10+1』 No.11 (新しい地理学) | pp.64-84
[対談]
移動とツーリズム | 今福龍太+吉見俊哉+多木浩二
Migration and Tourism | Imahuku Ryuta, Yoshimi Syunya, Taki Kouji
旅 — 観光と人類学のパラダイム・チェンジ 多木…今日は今福さんと吉見さんとの対談であって、私はオブザーバーなんですが、最初に今日話していただきたいことを、問題...らいまどこからでも「日本」は生まれてくる。 吉見俊哉旅のかたちの変容 吉見…最初に観光というもの...
『10+1』 No.02 (制度/プログラム/ビルディング・タイプ) | pp.170-186
[Urban Tribal Studies 12]
学び/まねび逸れる野郎ども(承前) | 上野俊哉
Unlearning to Raver (Sequel) | Ueno Toshiya
...の点をおさえる必要がある。 ★四──たとえば吉見俊哉の一連の作業にははっきりそうは書いていない... ...ているのでは、と思わせるニュアンスがある。吉見俊哉『カルチュラル・スタディーズ』(岩波書店、...
『10+1』 No.25 (都市の境界/建築の境界) | pp.205-214
[論考]
動物化するグラフィティ/タトゥー 都市/身体の表面への偏執 | 南後由和
Animalizing Graffiti / Tattoos: Paranoia on the Urban / Body Surface | Yoshikazu Nango
...四年度の東京大学大学院学際情報学府の講義(吉見俊哉教授、北田暁大助教授)を通じて主に飯田豊氏... ...トボーディング──都市下位文化の日常性」(吉見俊哉+若林幹夫編『東京スタディーズ』紀伊國屋書...
『10+1』 No.40 (神経系都市論 身体・都市・クライシス) | pp.144-155
[論考]
Tokyo Image:1990s──地下を廻って | 林道郎
The Tokyo Image 1990s: Around the Underground | Hayashi Michio
...の)ネットワークへと変化していったことは、吉見俊哉の指摘にあるとおりだが★一、地下鉄ネットワ... ...じめることが可能だろう……か。註 ★一──吉見俊哉『メディア時代の文化社会学』(新曜社、一九...
『10+1』 No.19 (都市/建築クロニクル 1990-2000) | pp.147-155
[論考]
現代都市の境界線──包装(ラップ)される都市と身体 | 若林幹夫
The Border of the Present City: The Wrapped City and the Body | Wakabayashi Mikio
...流通(セゾン)グループの軌跡を事例として」吉見俊哉編『21世紀の都市社会学4 都市の空間 都市の... ...隠蔽──寄せ場・山谷 一九四五─一九七五」吉見俊哉編『21世紀の都市社会学4 都市の空間 都市の...
『10+1』 No.25 (都市の境界/建築の境界) | pp.142-150
[プロジェクト・スタディ]
領域/公共圏──阿部仁史┼小野田泰明の思索/活動から | 小野田泰明
Territory/Public Sphere: From the Meditations and Works of Hitoshi Abe and Yasuaki Onoda | Yasuaki Onoda
...包させて発せられていく批判的な実践である(吉見俊哉、二〇〇一)。 こうした紹介からフランクフル... ...リティクス』(東京大学出版会、一九九九)。 吉見俊哉『知の教科書 カルチュラル・スタディーズ』...
『10+1』 No.25 (都市の境界/建築の境界) | pp.73-89
[都市論の系譜学 2]
批判の切断 | 上野俊哉
"Criticism"at a Critical Dvide | Ueno Toshiya
「アーバニズム」(都市論=都市計画)とは都市が抑圧し、排除し、外部化してしまった何ものかの投射、射影ではないだろうか? 一般に「アーバニズム」は、われわれが都市...ハリー・クリーヴァーが詳細に分析し★一五、吉見俊哉が現地での情報をふまえつつ語っているように...
『10+1』 No.02 (制度/プログラム/ビルディング・タイプ) | pp.274-285
[論考]
20 Years Before 1960. And Now──内田祥文から見える今の世界 | 金子祐介
20 Years Before 1960. And Now: Today Seen by Yoshifumi Uchida | Yusuke Kaneko
Uchida who? 最近のインタヴューで、レム・コールハースに対して磯崎新が「彼がもう少し長く生きていれば丹下健三の最大のライヴァルになったであろう」と語っ...一辺倒の経済問題を解き明かそうとしている。吉見俊哉も戦後を規定していく福祉行政国家=統制経済...
『10+1』 No.50 (Tokyo Metabolism 2010/50 Years After 1960) | pp.114-120
[政治の空間学 4]
Chap.2 都市に対して「リベラルである」とはどういうことか? 1 | 北田暁大
Chapter 2: What Does It Mean to be a "Liberal" City? | Akihiro Kitada
1 下北沢で起こっていること すでにご存じの方も多いと思うが、現在東京の世田谷区にある下北沢という街が「存亡の危機」に直面している。 下北沢といえば、新宿へと通...していただいた。記して感謝したい。 ★二──吉見俊哉は次のように述べる。「ディズニーランドは、...
『10+1』 No.40 (神経系都市論 身体・都市・クライシス) | pp.284-290
[都市表象分析 31]
都市表象分析とは何か(一)──自註の試み | 田中純
What is the Analysis of Urban Representation? 1: Attempting Self-annotation | Tanaka Jun
1 「非都市」という戦略 前回の論考は、拙著『都市の詩学』に対する趣向を変えたあとがきのようなものとなった。それが本連載を中心として、ここ数年の都市論やイメージ...不満だった。この著作が内田隆三、大澤真幸、吉見俊哉といった社会学の俊英たちとの対話のなかから...
『10+1』 No.49 (現代建築・都市問答集32) | pp.2-11
[論考]
景観の消滅、景観の浮上 | 若林幹夫
The Disappearance of Landscape, the Appearance of Landscape | Wakabayashi Mikio
1 景観の現在 「景観」という言葉が、そしてその言葉によって名指される何かが、今日、私たちの日常生活のなかに、共通の問題の場(トポス)のようなものとして浸透し...については、五十嵐太郎「日本橋と首都高」(吉見俊哉+若林幹夫編著『東京スタディーズ』紀伊國屋...
『10+1』 No.43 (都市景観スタディ──いまなにが問題なのか?) | pp.126-135
[グローバリズム 1]
ポストスクリプト?──グローバリズム論の前提 | 八束はじめ
Postscript?: An Assumption of Globalism | Yatsuka Hajime
1 前口上:グローバリズム、その私的再発見 我ながら最近の自分の立場なり関心とひどく懸け離れた主題を選んでしまったと思った。というと、過去の私の仕事を知る人々は...ない。そこで行なわれた座談会で口火を切った吉見俊哉(一時期原研究室に在籍!)が、九〇年代には...
『10+1』 No.31 (コンパクトシティ・スタディ) | pp.209-216
[建築を拓くメディア]
都市景観の変容をめぐる諸問題 | 若林幹夫
The Various Issues around the Change in Cityscape | Wakabayashi Mikio
森川嘉一郎は『趣都の誕生──萌える都市アキハバラ』(幻冬社、二〇〇三)で、未来の都市の景観を予想しようとする時、一九七〇年代までならば、建築家がつくる建築作品の...や構造の多層性を考えるためのガイドとして、吉見俊哉と私が編者となって最近作った本を紹介してお...
『10+1』 No.38 (建築と書物──読むこと、書くこと、つくること) | pp.132-133
[鼎談]
建築と書物──読むこと、書くこと、つくること | 隈研吾+五十嵐太郎+永江朗
Architecture and Books: Reading, Writing and Creating | Kuma Kengo, Igarashi Taro, Nagae Akira
建築と書物の親和性 永江朗──「建築家はどのように書物と関わるのか」というのがこの鼎談のテーマです。最初に素朴な感想をもうしますと、芸術家のなかで建築家ほど書物...〇〇四)です。ベンヤミンやコルビュジエから吉見俊哉、宮台真司、堀江敏幸までの、内外の都市論/...
『10+1』 No.38 (建築と書物──読むこと、書くこと、つくること) | pp.54-70
[論考]
没場所性に抗して | 本江正茂
Against Placelessness | Motoe Masashige
例えば「情報」や「場所」のように、あまりに一般的であたり前の概念は、幅広く、混乱しており、定義することが難しい。定義は往々にして同語反復に陥る。かといって、議論...リカ──テレフォンネットワークの社会史』(吉見俊哉+片岡みい子+松田美佐訳、NTT出版、二〇〇〇...
『10+1』 No.42 (グラウンディング──地図を描く身体) | pp.132-134
[対談]
「メディア都市の地政学」をめぐって 記憶/サイバースペース/テレポリティクス | 田中純+岩崎稔
On the Geopolitics of the MediaCity Memory/Cyberspace/Telepolitics | Tanaka Jun, Iwasaki Minoru
都市の政治学=社会学と均質空間 田中── 今回の特集は「メディア都市の地政学」と題しています。空間的な距離を無化するテレコミュニケーションが普及することによって...が悪いようですし、なかなか翻訳も出ません。吉見俊哉さんもあの対談でそこのところをついているの...
『10+1』 No.13 (メディア都市の地政学) | pp.62-77
[批評]
近代都市空間と公衆衛生 序論──後藤新平の衛生思想の臨界点へ | 加藤茂生
An Introduction to Urban Space and Public Health in Modern Japan: Toward the Critical Points of Goto Shimpei's "Hygienical Thought" | Kato Shigeo
1 「上からの衛生」批判と「身体の規律化」論 一九九〇年代に入って、日本の近代都市空間の形成を、公衆衛生に注目して新しい観点から論ずる論考が見られるようになっ...、一九九四)。 成田龍一「文明/野蛮/暗黒」吉見俊哉編『21世紀の都市社会学 四 都市の空間 都...
『10+1』 No.12 (東京新論) | pp.156-167
[論考]
拾い集めて都市と成す──泉麻人の街歩き | 成瀬厚
The City Constituted from the Pieces Collected: Asato Izumi's Town Walk | Atsushi Naruse
町のなかを移動する者、つまり町の使用者(われわれすべてがこの者である)は一種の読者なのであって、おのれに課されたさまざまの義務や必要な移動に従って、言表のいくつ...都市論ブームを踏まえた社会学的都市論である吉見俊哉『都市のドラマトゥルギー』(弘文堂、一九八...
『10+1』 No.29 (新・東京の地誌学 都市を発見するために) | pp.117-126




 PEOPLE
PEOPLE